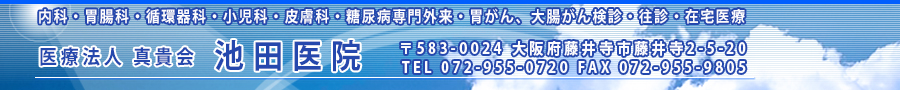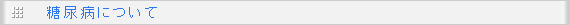 |
|
|
|
|
| ①適正な体重を維持する。 |
|
|
糖尿病の食事療法の基本は適正なエネルギー量を摂取することと栄養素をバランスよく摂取することです。
肥満の人は食事療法で少しずつ自分の標準体重(自分の理想的な体重)に近づけていくことが必要です。
また肥満を解消することだけで、糖尿病状態が改善することもあります。標準体重とは人間が最も活動的に日常生活ができる理想的な体重とされています。最近では、肥満かどうかの判定は、BMI(BODY MASS INDEX)
という指数が一般的でこの数値が25以上になったら肥満です。医学的にみてBMIの数値が22前後が最も病気にかかりにくく死亡率も低いといわれています。
|
|
|
| ②一日の摂取エネルギ-量を適正範囲にする。
|
|
|
当然食べ過ぎは肥満の原因となります。また食べ過ぎると糖質の処理をするため、インスリンの必要量が増加しその結果、膵臓のべ-タ-細胞に負担がかかり、さらにそのような状態が長く続くと膵臓が疲れきって、インスリンの分泌低下をきたし、糖尿病の増悪が出現することとなります。
それゆえ、適正なエネルギ-量の摂取を保つことが重要となります。
そのために自分自身の適正なエネルギー摂取量を知る必要があります。
医師は、患者さんの個々の状況に応じて1日の食事の適正な量(指示エネルギー量)を指示します。
例えば、標準体重70kg、肥満、軽労働の人は、
適正エネルギー摂取量=70×25=1750cal
と、なります。
|
|
|
| ③栄養のバランスのとれた食事を規則正しく摂る。
|
|
|
肥満を予防し、治療効果を高める。
適正なエネルギーの摂取とともに大切なのが、栄養のバランスで3大栄養素である炭水化物、たんぱく質、脂質を適切な配分で摂ることです。
一般的には、1日の総エネルギー量の55~60%を炭水化物で、15~20%をたんぱく質で20~25%を脂質で摂ることが目安となります。
栄養のバランスよく摂るコツは、腹7~8分目を心がけ偏食をせず、おかずの量を増やすのではなく、おかずの種類を増やすことです。
|
|
|
| ④ゆっくりと時間をかけて食べる。
|
|
|
食後の急激な血糖上昇を緩やかにすることが大切です。
食物繊維の多い食事も同様に、食後の高血糖や中性脂肪の吸収を抑えます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糖尿病の食事療法は、この食品交換表の示すところにそってされています。
糖尿病の治療のための食品交換表は、医師や栄養士が糖尿病食の指導を行うに当たって糖尿病の方々に分かり易く、しかもすぐ役立つようきめ細かな工夫がなされています。
|
|
|
|
|
|