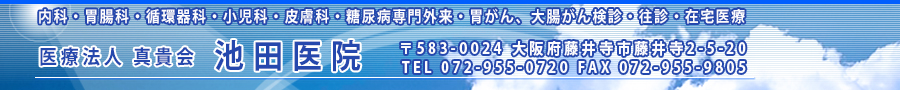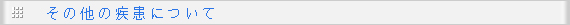 |
|
|
|
|
| 心房細動は不整脈の一種で心臓の心房部分が不規則震えて規則正しい拍動ができなくなった状態です。高齢者に比較的起こりやすいのが特徴で、高齢社会の現在、患者数は増加を続けています。 |
|
|
心臓の動く仕組み
|
| 心臓は、心筋という筋肉でできていて、左右の心房と心室の4つの部屋に分かれています。これらが連携して規則正しい拍動繰り返すことで、心臓は全身に血液を送るポンプの役目をしています。この拍動は、「洞結節」と呼ばれるところから発せられる電気信号によりコントロールされ、電気信号が特殊な繊維を通って心臓全体に伝わることで、心臓は規則正しく拍動します。 |
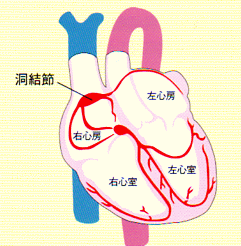 |
|
|
心房細動とはどのような不整脈?
|
|
心房細動は、心房がけいれんするようにとても速く小刻みに震えて、規則正しい心房の収縮ができなくなった不整脈です。心房細動そのものは直ちに命を脅かすもではありませんが、心房内に血栓(血液のかたまり)ができて脳梗塞の、原因になったり、心臓の機能が低下して心不全を引き起こすことがあります。
|
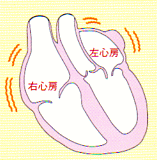 |
|
| 心房細動の原因 |
|
心房細動は心臓に病気のある人だけでなく、ストレスや不規則な生活週間によっても起こります。また加令や下記に示す病気の合併症など様々な原因が考えられます。
|
 |
|
| 心房細動の症状 |
|
下記のような症状があります。ただし、高齢者では、無症状のことも多く、定期健診の心電図検査で初めて見つかる場合もあります。
|
 |
|
|
心房細動の種類
|
|
心房細動は下記のように分類されます。発作性の心房細動はそのまま放置すると持続性の心房細動に進行することがあり、気になる症状があったら早めに医師にご相談下さい。
|
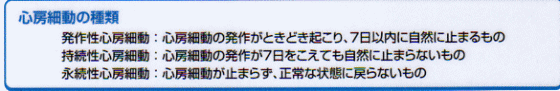 |
|
|
心房細動の頻度
|
|
心房細動は最も多くみられる不整脈で、欧米では40才以上に4人に1人が発症すると言われています。日本でも生活習慣の欧米化に伴い、心房細動の患者数は増加傾向あります。下記に日本の心房細動の患者数と将来の予測数を示しました。
|
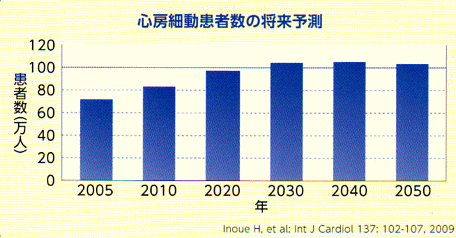 |
|
|
心房細動の検査法
|
|
心電図検査は、心臓に流れる電気信号を波形として記録するものです。心房細動があると、波形が不規則になり、通常は見られない細かな細動波があらわれます。短時間の一般的な心電図検査で異常がみつからなくとも、携帯型の心電図機器を装着して、24時間(1日)の生活を通して心臓の動きを記録するホルター型心電図を行うと、発作性の心房細動がみつかることがあります。心エコーは超音波を使って体の外から心臓の様子を観察するものです。心臓のかたちや、動き、血液の流れの異常などをみつけることができます。より詳細な心臓内の様子(心臓の弁の異常、血栓の有無)を検査するため経食道心エコー検査を行うこともあります。心不全の状態の把握のため、BNP(血液検査)も有用です。(BNP参照)
|
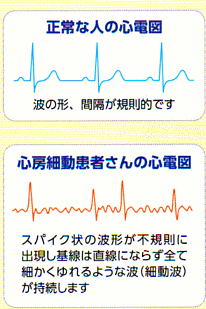 |
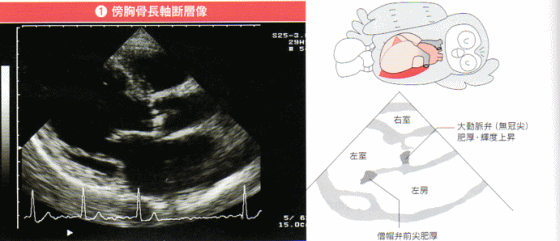 |
|
心房細動があると何が怖いか
|
|
確かに心房細動そのものは、ただちに生命を脅かすものではありません。しかし、心房細動があると、心房内の血の流れが乱れたり血液がうっ滞して、心房内に血栓ができやすくなります。血栓が心臓から飛び出して脳の血管を詰まらせると、脳梗塞を起こします。心臓からできた血栓が原因で起こる脳梗塞を「心原性脳塞栓症」といいます。心原性脳塞栓症を起こすと、寝たきり、半身麻痺、失語症など、重篤な後遺症を残す可能性が高くなることから、心房細動の患者さんは血栓をできにくくする治療を受け、脳梗塞を予防することが大切です。
|
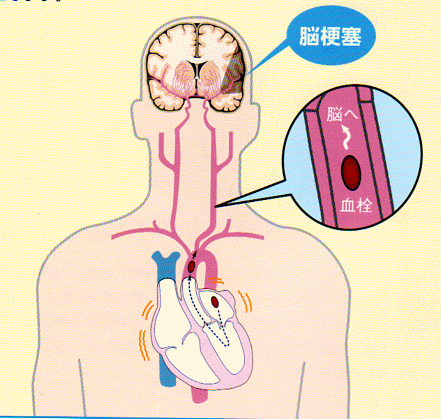 |
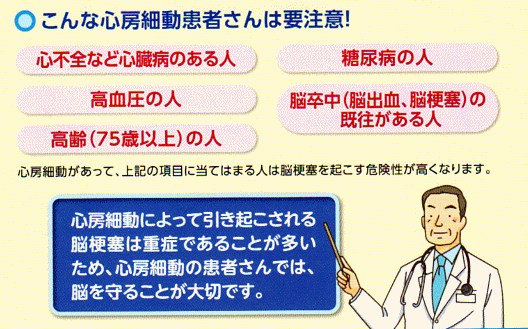 |
|
心房細動の治療
|
|
1)心房細動以外の病気や生活習慣の改善
2)脳梗塞の予防
3)心房細動そのものの治療
1)心房細動は弁膜症や心不全などの心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能亢進症等の基礎疾患があり起こっている場合があります。また疲労やストレス不規則な生活習慣が原因となっている場合もあり、したがって心房細動以外の病気の治療や生活習慣の改善で心房細動が起こらなくなることがあります。
2)心房細動が原因で起こる脳梗塞を予防するためには、血液を固まらせる働きを抑え、血液がかたまりやすくなっている状態を改善する治療が必要になります。現在抗凝固薬には「ビタミンK拮抗薬」最近発売された「直接トロンビン阻害薬」があります。
3)心房細動そのものお治療は抗不整脈薬を用いて患者さんの自覚症状を取り除いて日常生活の質を向上させます。また専門の医療機関ではカテーテルアブレーション治療や心臓ペースメーカーなど、薬を使わない特殊な治療も行われるようになっています。
|
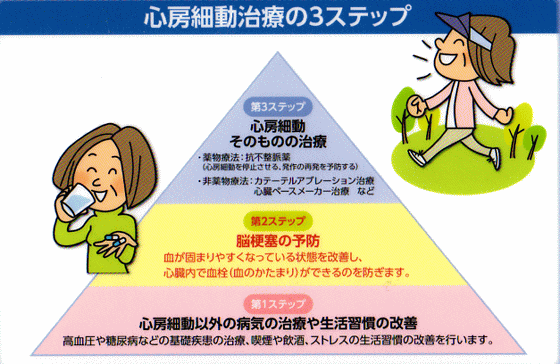 |
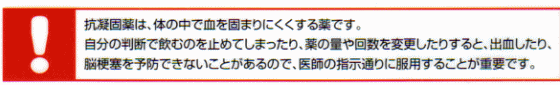 |
|
|
|
|