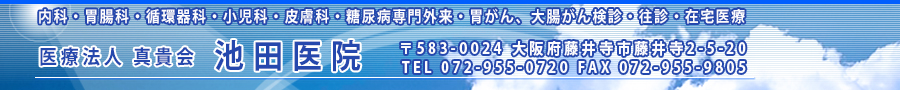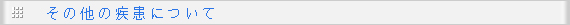 |
|
|
|
|
| 最近知られるようになりましたが、レストレスレッグス症候群という言葉はご存知でしょうか?「むずむずする」「虫が這っている」「ピクピクする」「ほてる」「かゆい」などの不快感が、脚の表面ではなく、内部(深部)で起こり、特徴は夕方や夜眠る前、長い間じっとしているときなどに脚に不快感があり、動かさずにはいられなくなる。何かに熱中すると症状弱まり脚を動かすことでも不快感が和らぎます。そのような症状を感じたら、それは「むずむず脚症候群」こもしれません。 |
|
|
| 有病率 |
| 加齢とともに有病率が上昇し、そのピークは60-70代といわれています。男女比率1:1.15でやや女性に多く、原因が特定されていない特発性(一次性)と他の疾患や薬剤が原因で起こる二次性に大別されます。有病率は人口の2-5%といわれています。しかしその病気の認知度が低いため多くの患者さんが見逃され、十分な治療を受けられないままになっているのが現状です。 |
 |
|
|
| 主症状 |
| 脚の不快感と脚を動かしたいという欲求がある。(脚の表面ではなく、深部に不快感があり、その不快感は患者さんによってさまざまな言葉で表現されます。むずむずする、虫が這う、痛がゆい、)動かないときに症状が強まる。(眠りに入るとき、じっとすわっているとき、横になっているときなど安静状態で脚がむずむずするなどの不快感が増しますが、何かに熱中すると症状が弱まります。)脚を動かすことで症状が軽快する。(患者は脚をたたく、さする、冷たい床に足をこすりつける、寝返りを繰り返す、などで不快感を軽くしようとします。重症になるとじっとしていられないので歩きまわったりします。)症状が現れやすい時間帯がある。(病初期には夕方や夜に脚のむずむず感があり、進行すると、昼間に症状が現れることがあります。病状に日内変動があるのがこの病気の特徴で、夕方から夜間に症状が増悪することが多く、睡眠障害を起こします。そのため日常の活動レベルを低下させるので、患者のQOL(quality
of life)が下がります。 |
 |
 |
|
|
| 診断基準 |
| 下に示す診断基準がすべてにあてはまれば、むずむず脚症候群の可能性があります。鑑別すべき病気も示しました。患者さんも何科に受診してよいのかわからない場合が多いようです。確定診断は睡眠障害の専門医や神経内科医によってなされます。 |
 |
 |
 |
|
|
| 問診表(重症度スケ-ル) |
| 下に示しました。 |
 |
|
|
| 病気のメカニズム |
| 残念ながら「むずむず脚症候群」の起こるメカニズムははっきり解明されているわけではありません。脳内の神経伝達物質のひとつ「ドパミン」の機能障害や『鉄欠乏」が関係していると言う説が有力です。「ドパミン」はさまざまな運動機能を潤滑にする働きをするものでこの「ドパミン」の合成に不可欠なのが「鉄」です。鉄が不足することでドパミンがうまく働かず、それが症状を引き起こすのではないかと考えられています。このように「むずむず脚症候群」には原因のはっきりわからない(一次性)以外にも、他の病気や薬剤によって起こるもの(二次性)のものがあります。二次性の原因としては、慢性腎不全(特に透析中)、鉄欠乏性貧血、妊娠、糖尿病、パ-キンソン病、慢性関節リウマチなどが挙げられます。 |
|
|
| 治療 |
| つらい症状を伴う「むずむず脚症候群」ですが、適切な治療をすれば多くの場合、症状は改善されます。非薬物療法は下に示しました。薬物療法はドパミンアゴニストが第一選択薬として推奨されています。 |
 |
|
|
|
|
|
|