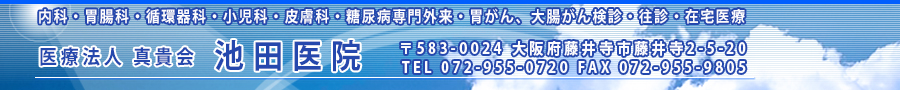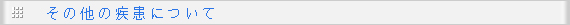 |
|
|
|
|
| 血圧の分類と降圧目標 |
| わが国において2004の高血圧治療ガイドラインが下図のように決められ、拡張期血圧が仮に90mmHg未満であっても収縮期血圧が140mmHg以上であれば「収縮期高血圧」と呼びます。診察室で測定する外来血圧の 降圧目標値は140/90未満とされていますが、このガイドラインでは、さらに年齢および臓器障害の有無でも規定されています。 |
|
|
| 成人における血圧分類 |
 |
|
|
| 成人における血圧分類 |
 |
|
|
| 降圧目標値 |
 |
|
|
| 最近わかってきた高血圧のタイプ |
外来血圧と家庭血圧
血圧は診察室で測定する外来血圧と自分自身で自宅で測定する家庭血圧に分けられます。最近、診察室の血圧だけでなく、家庭での血圧も血圧管理の上で非常に重要視されてきています。
|
|
|
| 外来及び家庭高血圧の定義 |
 |
|
|
| 仮面高血圧 |
診察室で測定する血圧は正常で、家庭で測定すると高くなるタイプです。次の2種類のタイプがあります。
1) 早朝高血圧・ 早朝に血圧が高くなるタイプで、高血圧を治療されている人の
約半分に認められるといわれています。
2) 夜間高血圧・ 夜間から早朝にかけて、寝ている間も血圧の高い状態が続く。
|
|
|
| 1日の変動からみた早朝・夜間高血圧のタイプ |
 |
|
|
| 白衣高血圧 |
仮面高血圧とは逆に家庭で血圧を測定すると正常で、診察室では高くなるタイプ。
|
|
|
| 早朝高血圧の怖い理由 |
|
高血圧の中で特に危険なのは早朝高血圧です。早朝高血圧は外来の診察室で測定すると正常で、治療があたかもうまくいっているようにみえるため見過ごされやすく、気づかないうちに脳血管障害や心臓病の発症する危険性が増加するといわれ、すでに高血圧の治療を受けている人にも多くみられます。早朝高血圧は前に述べたように早朝上昇型と夜間高血圧型があります。特に怖いのは夜間高血圧型です。早朝上昇型の場合は高血圧になっている時間がそれほど長くありませんが、それに対して夜間高血圧型は1日の約1/3もの間、血圧の高い状態が続いていることになり、脳、心、腎等の重要臓器に負荷がかかっていると考えられるのでより危険性が高いと思われます。
|
|
|
| 高血圧のタイプ別からみた脳血管障害や心筋梗塞の危険性 |
 |
|
|
| 血圧の自己測定 (自分の本当の血圧を知ろう) |
|
家庭で血圧を測定すると測定回数が増えるため、診察室での血圧測定に比べて血圧の変化が正確に把握できます。また服用している降圧薬の効果を確かめることもできます。早朝の高血圧は脳血管障害、心臓病などの発症と密接に関係していることが明らかになってきました。自分自身の本当の血圧を知ることは糖尿病での血糖自己測定(SMBG)と同様に高血圧の治療に参加できるということです。このように積極的な意志を持ってゆくことは合併症を抑制するという観点からも意義があることです。本内科でも血圧測定の結果を受診毎に持ってきていただいて、治療のよりどころとしています。家庭血圧の平均値が基準値135/85mmHGを超える日続いたら主治医に相談しましょう。夜間高血圧が疑われる方も自分にあった降圧治療を主治医と相談しましょう。
|
|
|
| 家庭で血圧を測るときのポイント |
 |
|
|
| 早朝高血圧のメカニズム |
|
早朝に血圧が高くなるのは、自律神経のバランスが変わるためと考えられています。自律神経は「交感神経」と「副交感神経」からなり、体のさまざまな臓器の働きをコントロ-ルしています。通常、夜寝ている間は「副交感神経」が働いて血圧も安定しています。一方、早朝は体を活動させようと、「交感神経」が働いて体が緊張状態になり、血管が収縮して血圧が上昇します。もともとある高血圧にこうした早朝の血圧上昇が加わるために脳血管障害や心筋梗塞などを発症する危険度が高くなります。また夜間高血圧型の早朝高血圧には、最近注目されている睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)が10%以上みられます。睡眠時無呼吸症候群では睡眠時に一時的に呼吸が止まることで酸素不足になり、心臓や血管に負担がかかるため血圧が上がります。
|
|
|
| 夜間と日中の血圧変動(交感神経と副交感神経) |
 |
|
|
| メタボリックシンドロームと早朝高血圧症 |
|
さらに交感神経の働きが高まる一因に、最近有名になったメタボリックシンドロ-ムが注目されています。メタボリックシンドロームでは過食・ストレス・運動不足などにより内臓に脂肪が溜まってきます。また睡眠時無呼吸症候群とも関連があります。内臓脂肪から、交感神経の働きを活性化させる物質が分泌されます。交感神経が活性化すると、血糖値や中性脂肪が徐徐に上昇し、同時に早朝の急激な血圧上昇などをきたします。メタボリックシンドロ-ムの基準値(定義)はトピックスのメタボリックシンドロームのペ-ジを参照してください。メタボリックシンドロームの血圧基準値は130/85mmHG以上と高血圧治療ガイドラインの基準値、140/90mmHGより低く正常高値血圧ですがストレスにより急激な血圧の上昇を引き起こしますので、血圧に注意し、内臓脂肪を減らすように努力しましょう。
|
|
|
| メタボリックシンドロ-ムと早朝高血圧の関係 |
 |
|
|
| 早朝高血圧の治療 |
家庭血圧の測定で自分の本当の血圧がわかれば、治療目標がはっきりしてきます。食事で血圧をさげる、運動で血行を改善させる、どのような薬をいつ飲むかなど主治医に相談してください。
食事療法・ 塩分の1日摂取量の目標は6g未満ですが、非常に味気なく思われるので、最初は8-10gからスタ-トしてうまく香辛料や薬味を使うなど一工夫するのもよいでしょう。ちなみに日本人の1日の食塩摂取量は平均11-12g程度だそうです。他にカリウム(野菜、芋、豆類に多くふくまれる。)をとることも大切です。ただし、腎機能が低下している人はカリウム摂取に制限のある場合があります。動物性脂肪の取りすぎは高コレステロ-ル血症、動脈硬化を促進させるので血中コレステロ-ルを増やす飽和脂肪酸を多く含む食品を避け、逆にコレステロ-ルを減らす不飽和脂肪酸を多く含む食品をとりましょう。
|
|
|
| 食事療法 |
|
塩分の1日摂取量の目標は6g未満ですが、非常に味気なく思われるので、最初は8-10gからスタ-トしてうまく香辛料や薬味を使うなど一工夫するのもよいでしょう。ちなみに日本人の1日の食塩摂取量は平均11-12g程度だそうです。他にカリウム(野菜、芋、豆類に多くふくまれる。)をとることも大切です。ただし、腎機能が低下している人はカリウム摂取に制限のある場合があります。動物性脂肪の取りすぎは高コレステロ-ル血症、動脈硬化を促進させるので血中コレステロ-ルを増やす飽和脂肪酸を多く含む食品を避け、逆にコレステロ-ルを減らす不飽和脂肪酸を多く含む食品をとりましょう。
|
|
|
| 栄養のバランス |
 |
|
|
| 血圧のコントロ-ルに役立つ栄養素 |
 |
|
|
| 脂肪と食品 |
 |
|
|
| 運動療法 |
 |
|
少し汗ばむ程度の運動を、休みながら20分ほど続けることを習慣にしましょう。コンスタントなウオ-キングを本内科ではお勧めしています。運動後は水分補給を忘れずに。(心臓に異常のある人は、先に主治医に相談しましょう。メディカルチェックも忘れずにしてください。運動療法は全身を動かして大量の酸素を取り込む有酸素運動を、無理なく続けることが効果的とされています。まずは1分間に脈拍数が100-120程度のウオーキング(早足の散歩)がお勧めです。これを毎日行うのが理想ですが、1日おきに1時間、あるいは週5-6回30分行えば効果が期待できます。ただ体調がすぐれなかったり、運動中に何か症状が出たら中止しましょう。とにかく無理をしないことです。
|
|
|
| 血圧と合併症の関係および体重と血圧の関係 |
 |
体重が1kg減ると血圧が約1.7mmHg低下します。
収縮期血圧が2mmHg低下すると脳卒中による死亡の危険性が約10%、心筋梗塞による死亡の危険性が約7%低下するといわれています。
|
|
|
| 早朝高血圧の薬物療法 |
 |
|
|
 |
|
|
|
|