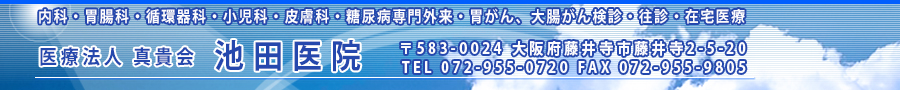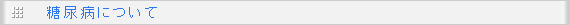 |
|
|
|
|
| 2010年7月1日より日本糖尿病学会は新しい糖尿病診断基準と国際標準化HbA1cを使用すると発表しました。その概要についての解説です。先ず正式な表記を示します。 |
|
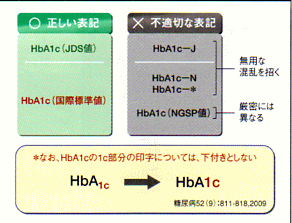 |
| 新しい糖尿病診断基準とその運用の目的とポイント |
1)HbA1cをより積極的に糖尿病の診断に取り入れ、糖尿病型の判定に新たにHbA1c値の基準を設ける。
2)血糖とHbA1cの同時測定を推奨し、血糖値とHbA1c値の双方が糖尿病型であれば1回の検査で糖尿病と診断可能にして、より早期からの糖尿病の診断・治療を促す。糖尿病型の判定にHbA1c値の基準値(JDS値)6.1%以上)を新設した。
3)現行のJDS値で表記されたHbA1c(JDS値)と、それに0.4%を加えNGSP値に相当する国際標準化された新しいHbA1c(国際標準値)を会誌「糖尿病」に掲載している「運用の実際」に則り適切に使用する。
|
|
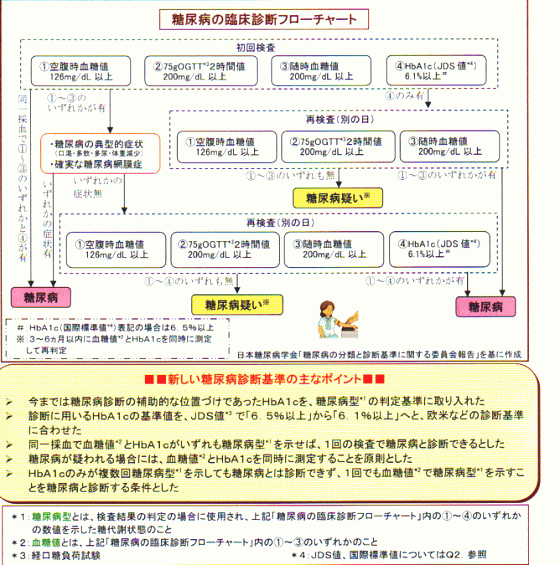 |
| HbA1cのJDS値・国際標準値とは?
|
| HbA1cの値は、今まで日本だけで使用されている「JDS(Japan Diabetes Society)」という1994年から日本国内で精度管理・標準化された値を用いていました。日本以外のほとんどの国では、「NGSP(Natinal
GlycohemoglobinStandadization Program)」という値が使われており、JDS値と比較して約0.4%高い値を示すという問題がありました。国際間のデ-タ比較時に数値の補正が無いまま使われたり、数値の違いが元で日本抜きの国際共同研究が進行したりする可能性もあるため、国際的に整合性を図る必要から国際標準化に向けた変更が検討されました。新しいHbA1cの値は、2010年7月1日から今までのJDS値に0.4%を加えた、NGSP値に相当する国際標準化された値(国際標準値)になりますが、混乱を避けるため、以下のような段階的運用が行われます。 |
|
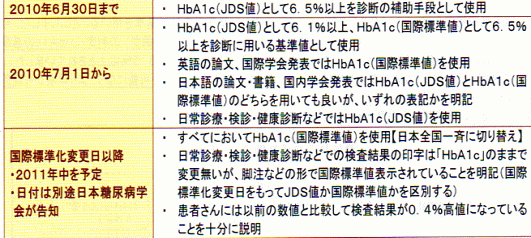 |
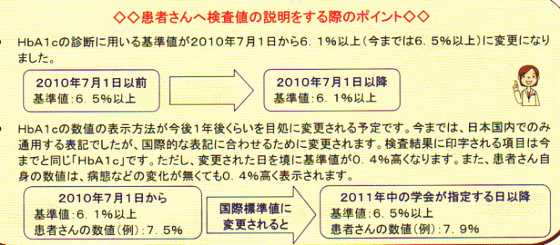 |
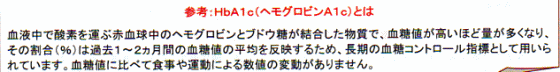 |
| 新しい糖尿病の診断 |
| わかりやすい表を追加しました。(2010) |
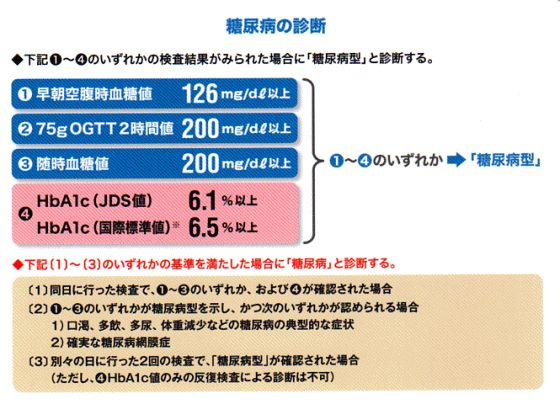 |
|
|
|
|
|
|